
#4 多彩な音に身を委ねると、冒険がはじまる。 |小林うてな×ラヴェル
長くて難解なイメージを持たれがちな、クラシック音楽の楽曲。現在のトレンド音楽にもそのエッセンスは散りばめられていますが、どんなふうに楽しんだらいいのかわからないという人も多いのではないでしょうか? この連載「名曲の『ココ』を聴こう」では、クラシック音楽にも影響を受けながら、ポップミュージックシーンで活躍しているミュージシャンたちがクラシック曲の聴きどころをピックアップし、その面白さを解説します。
第4回は、スティールパン奏者として〈D.A.N.〉や〈蓮沼執太フィル〉などさまざまなバンドのライブやレコーディングに参加する小林うてなさんが、ラヴェルの《マ・メール・ロワ》について語ります。《ボレロ》や《亡き王女のためのパヴァーヌ》などで知られるラヴェルが、知人の子どもたちのために描いたという5曲から成る組曲を、小林さんはどう感じ取ったのか。パーカッションをはじめあらゆる楽器をユニークな手法で用いるこの曲の魅力をたっぷりと語ってもらいました。
<教えてくれた人>
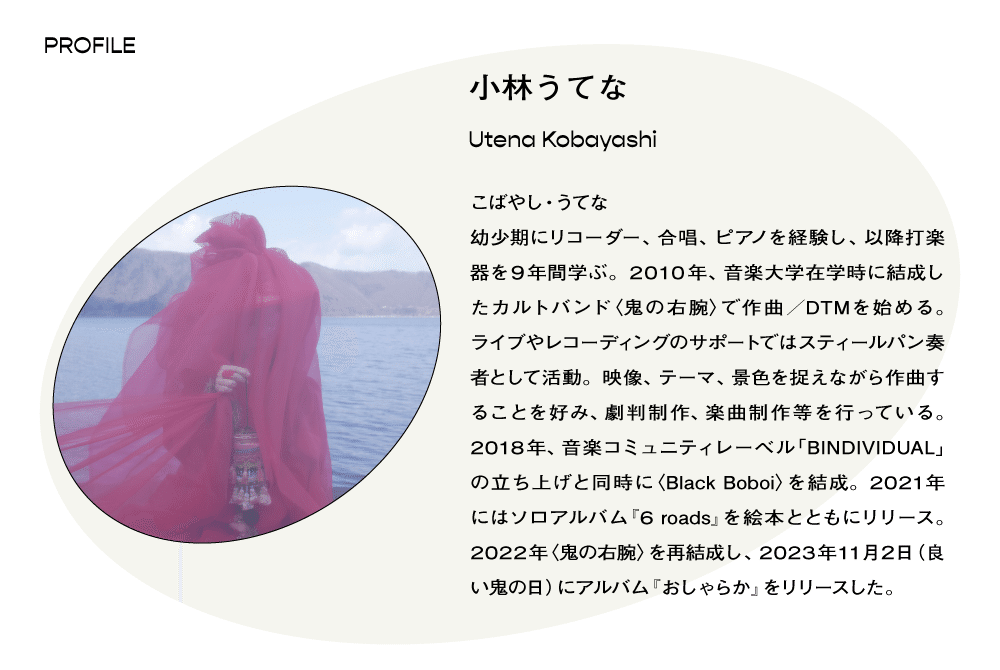
<解説する曲>
モーリス・ラヴェル《組曲「マ・メール・ロワ」》
指揮:ミシェル・プラッソン
演奏:トゥールーズ・キャピトル劇場管弦楽団
モーリス・ラヴェルがイギリスの伝承童謡「マザー・グース」をベースにして作曲したピアノ連弾の《組曲「マ・メール・ロワ」》。今回紹介するのは、それを管弦楽編曲した組曲版です。オリジナルの連弾曲は、1908年から1910年にかけて作曲、同年パリで初演されました。ラヴェルが友人であるゴデブスキ夫妻の2人の子ども、ミミとジャンのために献呈しましたが、幼い2人には難しく、フランスを代表するピアニストであるマルグリット・ロン(ロン゠ティボー国際コンクールの創設者の1人)の2人の弟子により初演されました。管弦楽組曲版はピアノ連弾版が初演された翌年、1911年に編曲されました。5つの曲から構成され、「眠りの森の美女」「一寸法師」「緑の蛇」「美女と野獣」の物語がモチーフになっています。
ラヴェルが作る楽曲は、聴いた瞬間に別の世界へと連れて行ってくれる。
私はクラシックの作曲家では、特にラヴェルとドビュッシーが好きなんです。ラヴェルの《亡き王女のためのパヴァーヌ》は、指揮者やオーケストラごとの違いを聴き比べたりもしましたね。「こっちのヴァージョンの方が好きだな」「なんでこっちはこんなに明るい演奏なんだろう?」って。ラヴェルの魅力は、聴いた瞬間に別の世界へと連れて行ってくれるところ。ドビュッシーもそうですね。「印象派」といわれるだけあって、どちらの曲も、目の前に景色がありありと浮かび上がってきたり、風を感じたりするんです。
実は《マ・メール・ロワ》は、他のラヴェルの曲に比べると、それほど馴染みがないんです。今回は、曲の背景など特に調べず、まずは自分が聴いてどう思ったか、どんな映像が頭に浮かんできたかを説明していきたいと思います。
Point1|
第1曲「眠りの森の美女のパヴァーヌ」[0:01〜]
音に誘われるまま、森の奥深くへ。
*第1曲「眠りの森の美女のパヴァーヌ」はこちら。
曲が始まった途端、もの悲しいような、切ないような気持ちになって、思わず涙が出そうになりました。わずか1分半の小曲なのですが、ゆったりと刻まれるリズムに導かれ、およそ15秒間隔で主旋律がどんどんバトンタッチされていく。それに合わせて自分の気持ちがどこかへ運ばれていくよう錯覚を覚えるんです。いつの間にか、森の奥深くへと誘われていくような気持ちになるのですが、解説を読むとこの曲は「眠りの森の美女」をモチーフにしているらしいんですよ。あの童話は森の中が舞台ですから、「なるほどなあ」と膝を打ちました。この曲、とても好きですね。
ちなみにパヴァーヌとは、宮廷における男女の厳かな舞踏のことらしいです。確かに、《亡き王女のためのパヴァーヌ》もこの曲も、一定のリズムがずっと刻まれている楽曲でしたよね。どちらも踊っているうちに、いつの間にか物語の世界に没入していくような、不思議な体験ができる楽曲です。
Point2|
第2曲「一寸法師」[01:57]
風や木々、動物たちが一体となった森が躍動する。
*第2曲「一寸法師」はこちら。
この曲も、四分音符でずっと伴奏が刻まれ続けているのですが、それに合わせて風が木々の葉をざわめかせたり、木の枝や蔦が伸びたり縮んだり、森全体が一つの生命となって躍動しているような映像が頭に浮かびました。開始から1:57あたりで、ピッピッと鳥の鳴き声のような音が入ってくるのもユニークですよね。森に棲む様々な動物や、木々が蠢く夜の森は恐ろしくもあるのですが、曲が終わると同時に夜も明けて、なんの変哲もない「森の中のただの日常」が戻ってくるんです。
解説を読むと、森に置き去りにされた一寸法師が途方に暮れているお話のようですね。四分音符の伴奏は、不安要素、おぼつかない足取り、迷い込むということを表現しているそうです。私の印象も、それほど見当違いではなかったようですね(笑)。
Point3|
第3曲「パゴダの女王レドロネット」[1:10]
多彩な楽器の音色に耳を澄ませてみる。
*第3曲「パゴダの女王レドロネット」はこちら。
最初に聴いたときは、笹舟に乗って「魔法のお城」を探検していく物語のように感じたんですよ。でも、何度か繰り返し聴いているうちに印象が変わっていきました。まず、開始から1:10あたりで銅鑼(ドラ)が鳴った瞬間にびっくりします。「え、銅鑼?」って。そこからスイッチが入って、とってもエキゾティックな曲だということに気づきました。
解説を読むと、この曲は中国の首振り人形のお話で、東洋的な5音音階をフレーズに用いるなど、すごくわかりやすく中国風味を入れていたんですよね。特に0:56からのセクション。不思議な変拍子の上で、鉄琴や木琴がものすごく速いパッセージで動いているのですが、解説を読むまで気づかなかったのが不思議なくらいオリエンタルな響きです。使われているのが西洋の楽器だから、すぐに気づかなかったのでしょうか。とにかく、いろんな楽器が登場するし、変わった使われ方をしている楽しい曲です。
Point4|
第4曲「美女と野獣の対話」[3:00]
理解不能だからこそ、答え合わせまで楽しめる。
*第4曲「美女と野獣の対話」はこちら。
これは、「なんのこっちゃ?」と思いながら聴いていました(笑)。導入部分は、月明かりに照らされた湖のイメージ。穏やかだけど、徐々に不安が忍び寄ってきているような雰囲気です。かと思えば、開始からおよそ3:00あたりで突然シンバルが大きく打ち鳴らされ、一瞬の静寂のあとハープが駆け上がるようなフレーズを奏で、トライアングルの「チーン」という合図に高音域のヴァイオリンがゆったりと演奏を始めます。「え、ふざけてるの?」って(笑)。
解説を読むと、この曲は「美女と野獣」がモチーフなんですよね。例えば、1:11あたりからものすごい低音楽器が主題を演奏するのですが、これはコントラファゴットで野獣を表現しているのだとか。シンバルが鳴らされる部分は、野獣に変身させられていた王子の魔法が解けるシーンを描写している。「なるほど!」と思いつつ、物語のディティールをこれだけ音に落とし込んでいると、逆にそれを知らずに聴くと「ヘンテコな曲だなあ」と感じますよね。そういう発見もありました(笑)。
ちなみに私はこの曲を聴いて、ものすごく優雅なウサギとでっかいカバかゾウの物語をイメージしました(笑)。「美女と野獣」から、そんなに遠くないと思いませんか? ただ、この曲がサティの《ジムノペディ》へのオマージュというのはよくわからなかったです。そんなふうに、自分の印象と楽曲の解説を照らし合わせてみるのも楽しいですね。
Point5|
第5曲「妖精の園」[2:24〜3:02]
人生でもっとも最高の瞬間が訪れる。
*第5曲「妖精の園」はこちら。
曲が始まった瞬間に、自分の人生の中でもっとも最高の瞬間を迎えたような気分になったんですよ。周りの景色も光り輝いて、夢の中にいるような気持ちになって。特に2:24くらいから3:02くらいまでのところは、長くゆっくりとクレッシェンドしながらクライマックスへ向かっていくんです。「今が人生で最高の瞬間……!」という気持ちになりました。
ただ、3:02でクライマックスを迎えてからは、グロッケンがキラッキラ、ティンパニもダンドンと打ち鳴らされて、「あ、これっておとぎ話だったんだ」と我に返るんです。現実の世界に引き戻されるような感じですね。何度聞いても、そこで物語と自分が切り離される感じが面白いですね。解説を読むと、この曲は「眠れる森の美女」がモチーフで、まさに物語がハッピーエンドを迎える瞬間に立ち合っているんだなと。「めでたし、めでたし」と言って、本を閉じるような感じ。本の中で物語は続いていますが、読者である私たちは日常の生活へ戻っていく。それを曲で表しているように思いました。
無理に分かろうとしなくていい。
ただ音を浴びてみるだけで、途端に好きになる。
私自身、音楽大学に通っていたときはコンサートホールで聴くほとんどの音楽が「苦痛」だったんです。まずじっと座っているが苦手だし、長かったり退屈だったりすると起きていられなくなるし、現代音楽に至っては、意味が全くわからなくて辛い、でも試験があるから聴かなきゃ……みたいな(笑)。ずっとクラシックに対して苦手意識があったんですけど、考えてみればそもそも中高生の頃はドビュッシーやラヴェルが好きだったわけだから、おそらくクラシックそのものとは別のことが原因で苦手になっちゃったと思うんですよね。
音楽大学を辞めてから、少し意識が変わりました。まず「分からないこと」を無理に分かろうとしない。そこにある「音」を、ただ聴くということに集中するようにしてみたんです。別に曲の意味や背景なんて、知らなくてもいい。もちろん、興味のある人はどんどん深掘りしていけばいいけど、まずは「ただ好き」でいいんだと思うようしたら、徐々に好きなクラシック曲が増えていったんですよ。そうすると、今度はそれを生で聴きたくなる。普通のポップスだってそうですよね。まず「あ、この曲いいな」と思って、そこから曲やアーティストについて調べたり、ライブへ足を運んでみたりするわけで。
実際のところ生のオーケストラを聴く体験は、何ものにも代え難いものがあります。だから、「この曲いいな」「この作曲家、好きだな」と思ったら、ライブハウスへ行く感覚でコンサートにも行ってみてほしい。きっと、新しい扉が開けると思いますよ。
小林うてなさんに解説いただいた、ラヴェルの組曲《マ・メール・ロワ》が聴ける公演はこちら。
■第2001回 定期公演 Aプログラム
指揮:トゥガン・ソヒエフ
曲目:ビゼー(シチェドリン編)バレエ音楽《カルメン組曲》
ラヴェル 組曲《マ・メール・ロワ》
ラヴェル バレエ音楽《ラ・ヴァルス》
日時:
1日目 2024年1月13日(土) 開演 6:00pm [ 開場 5:00pm ]
2日目 2024年1月14日(日) 開演 2:00pm [ 開場 1:00pm ]
text / Takanori Kuroda photo(Ravel) / aflo

